文字もパソコンで入力して、文字を書く機会は昔と比べると少なくなっています。
書類に記入する時に「きれいな字」が書ければ?と思った人もいると思います。
きれいな文字を書けるとただそれだけで、あなたの知性と品位をあげてあなた自信のイメージアップにつながります。
習字を始めたいけど、どうやって練習すれば良いのかわからない人のために必要なことを紹介します。
筆の持ち方は単鉤法(たんこうほう)と双鉤法(そうこうほう)!
単鉤法(たんこうほう)とは?
単鉤法は親指と人差し指と中指で持ちますが、前方からみた時に人差し指だけが筆の前から見えて中指は筆の後ろで挟む持ち方が単鉤法です。

双鉤法(そうこうほう)とは?
双鉤法とは、人差し指だけでなく、中指も前から見える持ち方が双鉤法です。
筆を持って書いてみて自分の書きやすい持ち方を決めてください。
筆の穂先に近い軸を持つことはおすすめしません。

ある程度書くことに慣れてきて、楷書より少し崩してスピードを出したり、リズミカルに書く時に、自由自在に筆と腕を動かすためには穂先よりある程度上、筆軸は大筆で20cmあります。
真ん中の10cm位の位置を握るほうが自由自在に筆とともに腕も動かしやすいです。
書道初心者におすすめの練習方法基本的な姿勢!
書く時の姿勢
椅子に腰掛けて書く或いは、座布団に座って書きますが、机に対して真っ直ぐ正面に座ります。
正座で上半身は背筋を伸ばして座ります。
机は椅子の時も正座のときもおヘソの高さが書きやすい高さです。
習字の時の服装
言うまでもなく袖の大きく開いた服装は墨が付きやすいので極力控えましょう。
書道の練習の時は、できる限り古い上着や最悪の時は捨てても惜しくない服があればそういう服を使用しましょう。
万一服に墨がついた時は、家庭用の歯磨き粉を大豆位、墨の付いた箇所に塗り込んでこすると歯磨き粉の漂白作用で白くなります。
覚えておくと万一の時に便利です。
書道初心者におすすめの練習方法・書道の三要素!
書道には重要な三要素があります。
筆法(ひっぽう)、筆意(ひつい)、筆勢(ひっせい)を書道の三要素といいます。
筆法(ひっぽう)=腕の構え方、筆の持ち方、筆の運び方、筆遣いなど筆遣いすべてを指す言葉です。
筆意(ひつい)=筆を運ぶ時の書き手の意図心構え、気持ち感情。
筆勢(ひっせい)=筆の勢い、力。
人が書いた作品は上の三要素によって見る人の印象が変わります。
筆画(ひっかく)
文字は複数の線で構成されています。
その1本1本を筆画(ひっかく)或いは点画といいます。
画数=筆画の数、筆順とは筆画を書く順番をいいます。
基本点画とは?
基本点画とは書道の基本となる点画のこと。
種類は8つあります。
これについては、他の記事で紹介していますのでその記事を参考にしてください。
書道初心者におすすめの練習方法・臨書をしてみる!
臨書とはどんな事!
どのような分野にも「古典」という存在があります。中国書道の古いものを「古典」といい、日本書道の古いものを「古筆」といいます。
臨書とは、そういう「古典」や「古筆」をそのままそっくりに書く練習方法です。
臨書には形をそのままに真似る「形臨」。
単純に形だけを真似るのではなく、書いた人の筆意を感じ取りながら書く「意臨」があります。
何回も繰り返し練習を重ねることで、古典の手本を見なくても記憶で臨書をかけるようになることを「背臨」(はいりん)といいます。
書道初心者におすすめの練習方法・書道の書体!
楷書=漢字の全ての筆画を続けて書かず筆を紙から離して書く書体です。
行書=漢字の書体の一つで、筆画をところどころ続けて書いたり省略したり、筆順がいれかわったりします。
楷書を少し崩しただけで読むことは難しくありません。
草書=早く書くことを目的とした書き方です。点画が省略されていて元の文字(楷書)が不明なものも少なくありません。
篆書=最も歴史ある書体です。転折などを一画でカーブさせて書くのが特徴です。身近なものでは印鑑の文字が篆書で掘られています。
隷書=横画は水平、縦画は垂直で、文字の形は左右対称です。筆運びは一定で筆遣いに隷書ならではの波のようにうねって見える「波磔」(はたく)と言われる線で特徴があります。
篆書を簡素化した文字が隷書で隷書から草書と行書、そのご楷書が誕生しました。
5つの書体がありますが、書道で学ぶ順序は楷書、行書、草書の順に勉強します。
隷書や篆書は長年書道を習っても一度も書いたことがないと言う人がほとんどかと思います。
書道初心者におすすめの練習方法!
書道は様々な流派がありますし、流派によって趣が全く異なります。
流派によって美しいとする特徴に違いがあります。
まず展覧会に足を運んで見学されることをおすすめします。
初心者に容易に書けるものではありませんが、展覧会ほど流派の作風が明らかにわかる場所はありません。
そこで自分の好みかそうでないかを確認して、自分の好みの書風の先生について勉強されることをおすすめします。
そうすることによってモチベーションも上がりますし上達も早いです。
書道初心者におすすめの練習方法書籍!
書道初心者におすすめの臨書のための古典、是非参考にして下さい。
お手本として長く使えます。
楷書
欧陽詢 「九成宮醴泉銘」二玄社
褚遂良 「雁塔聖教序」 二玄社
顔真卿 「多宝塔碑」 二玄社
行書
王羲之「蘭亭序」二玄社
まとめ
筆法(ひっぽう)、筆意(ひつい)、筆勢(ひっせい)を書道の三要素といいます。
筆法(ひっぽう)=腕の構え方、筆の持ち方、筆の運び方、筆遣いなど筆遣いすべてを指す言葉です。
筆意(ひつい)=筆を運ぶ時の書き手の意図心構え、気持ち感情。
筆勢(ひっせい)=筆の勢い、力。
臨書には形をそのままに真似る「形臨」。
単純に形だけを真似るのではなく、書いた人の筆意を感じ取りながら書く「意臨」があります。
何回も繰り返し練習を重ねることで、古典の手本を見なくても記憶で臨書をかけるようになることを「背臨」(はいりん)といいます。
記事で紹介したことを参考にしながら、書道を始められる動機になることを願っています。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。
宜しければこの記事も読んでください

オンライン絵画教室
通塾の必要がありません、小学生一年生からお絵かきがしたい子供達は、どうぞのぞいて見て下さい。

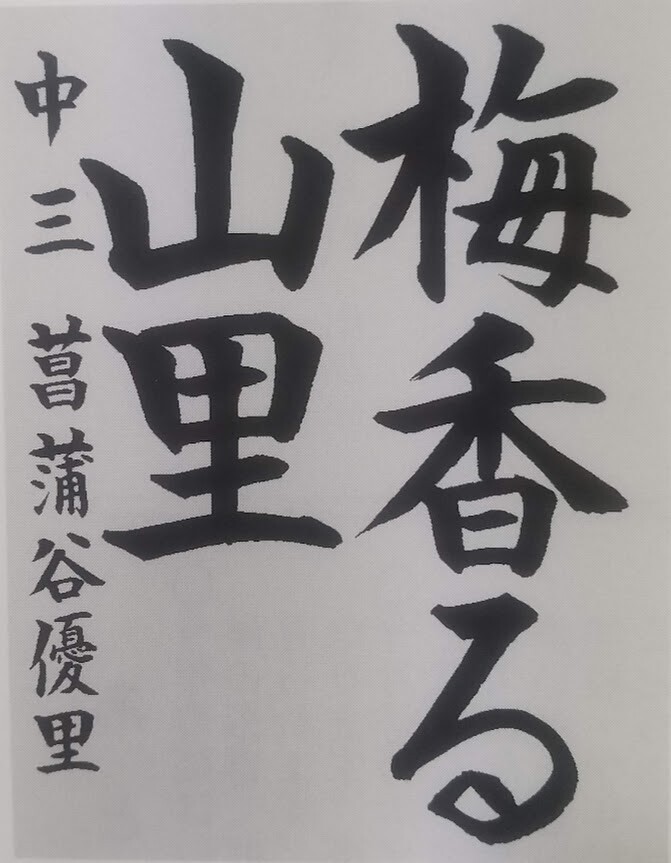


コメント