私達が子供の頃、普段何気なく聞いたことのある子ども向けの歌、「唱歌」と「童謡」「わらべうた」。
「わらべうた」と「唱歌」「童謡」の違いに付いて、普段はあまり意識した事は無いですよね。
この記事では、「唱歌」と「童謡」、「わらべ歌」の違いについて紹介します。
「唱歌」と「童謡」「わらべ歌」の違いは?
「唱歌」と「童謡」や、「わらべ歌」、聞いていて、童心に帰り懐かしく思い、心に安らぎを感じる歌が、多いのではないでしょうか。
「唱歌」とは?
「唱歌」とは、明治の学制から1941年までに作られた学校教育用の歌です。
日本の教育では、明治時代になって小、中学校で「唱歌」という科目を習うようになります。
現在の音楽です。
西洋の(旋律)メロディーに、日本の歌詞を付けたものが多くありました。
唱歌とは、文部省唱歌の事で、学校教育のために作られた歌で、著作権は文部省が所有し、作詞、作曲者は明らかにされなかったそうです。
卒業式で歌う「蛍の光」は原曲はスコットランド民謡です。それと「仰げば尊し」の原曲はアメリカの曲です。
幼児が歌う「むすんでひらいて」の原曲、「見わたせば」の旋律は、哲学者ルソーの作曲と言われています。
明治20年代になると、日本人の作曲も次第に数多く、増えていきました。
しかし、作詞の殆どが、親に孝行する内容の歌詞であったり、国への忠誠心などの道徳教育のような歌詞画がほとんどです。
芸術性や創作性よりも、道徳性を主にした歌詞です。
当時の文学者達によって、子どもたちに親しまれ、なおかつ、芸術的にも優れた歌を作ろうという事で生まれたのが、現在の「童謡」です。
「童謡」とは?
「童謡」は、大人が子供達のために作曲した歌で、学校教育のために作られた歌です。
大正時代以降、子供のために作られた歌を童謡といいます。
それ以前の道徳性だけを主にした、歌ではなく芸術性も取り入れた歌を作るようになりました。
きっかけは、「赤い鳥」と言う児童文芸雑誌が創刊されてからです。
1918年に創刊された雑誌「赤い鳥」は童謡を生み出すきっかけになりました。
童謡とは、「赤い鳥」の創刊以後に子供たちのために作られてうたです。
「赤い鳥」以降の代表的な作詞は、北原白秋、野口雨情、西條八十など。
作曲家では、山田耕筰、中山晋平などが代表的な作曲家です。
北原白秋、野口雨情、西條八十は、「童謡三大詩人」として活躍しました。
「この道」、「シャボン玉」、「肩たたき」が彼らの作品です。
童謡運動はその後、昭和初期から戦後まで約40年もの長い間文化運動となりました。
その後、その時代にあわせて大きくひろがっていきました。
現在でも、歌い継がれている「童謡」があるのは、40年という長い歳月をかけた運動があったからです。
童謡とは大正時代に、鈴木三重吉が北原白秋の協力を得て、児童文学の発展のために力を尽くして、大人が子供のために、作曲した歌です。
この作詞家や作曲家によって創作童謡が誕生しました。
「わらべうた」とは
「わらべ歌」は、子ども達を取り巻く、生活や遊びの中で、親や祖父母から伝わった歌、子ども達から自然に創り出された歌の事です。
子守唄や遊びの歌などで、大人から引き継がれた歌や子供が自然の中で作詞、作曲した歌です。
わらべ歌は、童謡や唱歌みたいに具体的な年代や作詞、作曲者の名前などは、不明の物が多いです。
日本最古のわらべ歌は万葉集に残っていることから、奈良時代には存在していたことが判ります。
童謡や唱歌と比較すると歴史の長さが判ります。
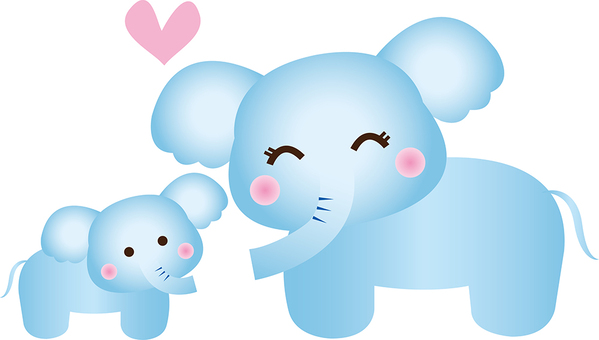
「唱歌」「童謡」「わらべ歌」の違いは?
「唱歌」明治初期から終戦までに作られた学校教育用の歌。
「童謡」は大正時代以降、子供たちのためにして作られた歌。
「わらべ歌」子供たち自身が遊びの中や自然の中で作り出した歌。
「唱歌」は明治の初期から作られて、第二次世界大戦が終わる頃まで学校教育の一端として歌われていました。
「唱歌」よりも後に出来たのが「童謡」です。「童謡」は大正時代以降に子供たちのために作られ、現在でも歌い継がれている歌があります。
作られるようになった目的は、それぞれに異なります共通している事は、子供達の間で歌われ続けた歌で、歌詞が簡単で覚え易いのが特徴。
まとめ
「唱歌」とは、明治の学制から1941年までに作られた学校教育用の歌です。
「童謡」は、大人が子供達のために作曲した歌で、学校教育のために作られた歌です。
「わらべ歌」は、子ども達を取り巻く、生活や遊びの中で、親や祖父母から伝わった歌、子ども達から自然に創り出された歌の事です。
作られるようになった目的はそれぞれに異なりますが、共通している事は、子供達の間で歌われ続けた歌で、歌詞が簡単で覚え易いのが特徴。
自然をゆっくりと観察しながら、誕生した素朴な歌が多いので心に染みますね。
素晴らしい歌を、これからも歌い継いで欲しいと思っています。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。
宜しければこの記事も読んで下さい。


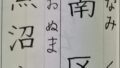

コメント